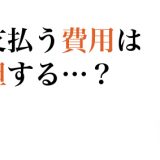家族や親族、いわゆる身内が亡くなった場合、遺された遺族が行う事柄に「遺品整理」があります。故人の家の片付け、持ち物を整理することです。物の量に関しては個人差ありますが、一般的な戸建住宅であれば相応の荷物が出てきて負担も大きくなってきます。
そして気になるのが遺品整理は誰が主導となって行うのか?
一般的に考えると故人に子がいれば子供が遺品整理を行う義務があると思っている方は多いと思います。通常であれば故人の子供が主導を取り遺品整理を行うのが正しいです。
しかし、例外もあります。「遺品整理は誰が行うのか?」しっかりと覚えておくと当事者になった場合もトラブルを未然に防ぐことが可能です。
遺品整理は相続人が行う
遺品整理と言うのは厳密に言えば遺族ではなく相続人が行う義務となります。遺品は故人が亡くなった段階で相続人の所有物となります。そして民法で相続人の順位付けが定められています。
法定相続人
法定相続人は民法で定められた相続人を示す順位付けを示しています。遺言書に相続人に関する記載がない場合は法定相続人で定められた対象者が相続人となります。
第一順位の相続人
故人(被相続人)に子がある場合、子と配偶者が相続人となります。もし子が被相続人より先に亡くなった場合、直系卑属が相続人の対象となります。(直系卑属は孫、ひ孫等)
第ニ順位の相続人
故人に子、直系卑属がいない場合は直系尊属と配偶者が相続人となります。(直系尊属は父母、祖父母等)
第三順位の相続人
故人に子、直系卑属、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続人となります。
配偶者は常に相続人となりますが、近年では離婚や再婚が増えており、相続人が複雑化されてきています。知らぬ所で相続人になっておりトラブルに巻き込まれる可能性もあるので自分の立ち位置をしっかりと把握しておくことも大切です。
相続人の例外
遺言状に相続に関する対象者が記されていた場合は遺言状に従って相続が行われます。
遺言状がない場合は上記の法定相続人で定められた対象者が相続人となります。
相続放棄といった手段もあり
相続人となった場合、故人の遺品・遺産を相続する形になりますが、相続がデメリットになるケースも存在しています。
例えば、故人が借金を背負ったまま亡くなった場合、借金は相続人が引き続き支払う形になります。
このような場合、相続放棄をすることで遺産の相続はできませんが、相続人では無くなるため借金の返済をする義務は発生しなくなります。
法定相続人の順位で例えると第一順位の対象者が相続放棄をすれば下位順位である第二順位の対象者が相続人となります。
相続放棄は親族間でのトラブルに発展する可能性もあります。相続や相続放棄に関してはよく相談の上、結論を出していくようにしましょう。また遺品整理と相続放棄は関係性が存在しています。
相続人対象者は遺品の一部を処分した場合、以降、相続放棄ができなくなります。もし相続放棄を検討している場合は遺品に触れずに相談を設けることが必要です。ただし、価値のないゴミの処分などは許されています。